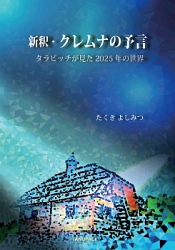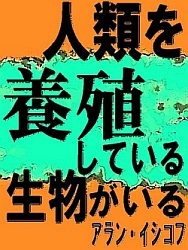ペリー来航後の日本
日本を開国させたのはハリス
 イシモリ:
イシモリ: さて、
ペリーは実際には日本の開国に失敗したと言ったけれど、では実質上、日本を開国させたのは誰かな?
凡太: え? 坂本龍馬ですか?
イシ: 違う違う! 龍馬の正体についてはもっと後で検証していくけど、ここではシンプルに、日本に貿易をさせることに成功した人物という意味。
それは
タウンゼント・ハリス(1804-1878)だ。学校ではペリーのことばかり強調されて、忘れられがちだけれど、ハリスという人は戊申クーデター前までの日本において大きな役割を果たしている。
ペリーが幕府と結んだのは「日米和親条約」で、アメリカが最大の目的としていた貿易の自由は1ミリも実現できなかった。その意味で失敗交渉だったわけだけど、この和親条約の中には「必要と判断されるときは、外交官を派遣することを許可する」という項目が盛り込まれていた。
この項目に注目して、ぜひ自分をその外交官として日本に派遣してほしいと売り込んだのがタウンゼント・ハリスだ。
ハリスは貧しい商人の家の六男として生まれて、初等教育しか受けていないんだけれど、独学でフランス語、イタリア語、スペイン語を学び、42歳のときにはニューヨーク州の教育局長になっている。
その後、家業が苦しくなったのを助けるために清、ニュージーランド、インド、マニラなどに行き、貿易を通して東洋に対する興味を高じさせた。
ペリーが結んだ日米和親条約を読んで、日本の初代領事になりたいと自分を売り込んだ。
凡太: ハリスさん、軍人でも官僚でもない民間人出身だったんですね。
イシ: そこが面白いよね。大統領から、
日本を武力に頼らず平和的に開国させ、他の国の専制的介入を防ぎつつ、アメリカとの貿易ができるようにせよ、という任務を託されて乗り込んできた。
でも、幕府としては寝耳に水で、そんなことは和親条約にはなかったはずだと言って追い返そうとしたんだけど、ハリスは頑として引かず、条約のここにちゃんと明記してあると主張して、とうとう下田の玉泉寺という寺に領事館を構えた。
領事旗を掲げたときの日記には「この帝国における最初の領事旗を私は掲げた。新しい時代が始まることは疑いない。これは日本の真の幸福につながるだろうか?」と書いている。
ハリスは江戸の将軍に謁見したいと再三申し入れたが、
水戸の徳川斉昭ら、攘夷論者たちの猛反対で受け入れられなかった。しかし、その間もペリーが結んだ和親条約(横浜条約)の細部を手直しした改定版和親条約ともいえる「下田条約」を改めて締結することに成功している。
安政4(1857)年7月、大砲を積んだアメリカの艦が下田へ入港したことで、幕府はこれ以上ハリスを下田にとどめておくことは難しいと判断して、江戸城での将軍謁見を許可した。
凡太: そのときの将軍は13代・家定ですか?
イシ: そうだね。主席老中だった阿部正弘が死んで、
堀田正睦が老中首座となっていたんだけど、
井伊直弼が実権を握りつつあったときだ。
井伊は雄藩諸侯を結束させて、交渉を許容するべきだという意見書を提出した。
その結果、幕府としては開国に踏み切ることを決めて、下田奉行・井上清直と目付・
岩瀬忠震がハリスとの交渉を開始した。
江戸城詰めの諸侯が条約交渉に反対しなかったのは、将軍の前で終始穏やかな態度で親書を読み上げたハリスの姿に、諸侯が感銘を受けたからともいわれている。
凡太: ハリスさん、なかなかの人物だったんですね。
イシ: 苦労人だし、自ら日本に行って領事を務めたいと売り込んだくらいだからね。
ただ、堀田も井伊も天皇の承諾(勅許)なしでの条約締結はまずいと思っていたので、老中首座・堀田正睦が勅許をもらうために京都へ向かった。
しかし、
岩倉具視や中山忠能らの根回しで、主に中・下級の公家たちが反対に回り、勅許は得られなかった。
当時の公家は、世界情勢も知らなければ、政治のノウハウも知らない。ただただ「
夷狄(外国人)は怖ろしい」と恐れおののいたり、「今さら朝廷に政治のことなんか相談されても無理に決まっている」と無関心を決め込んだり、まったくお話にならない。
そんな中で、下級公家の中には、これは幕府を倒す絶好のチャンスだととらえて、口八丁と謀略を武器にして倒幕の野望を膨らませていく岩倉具視のようなのが出てくる。
岩倉は「従四位上・侍従」という階位で、公家の中でも相当下のほうにいたんだけれど、この男の
フィクサーとしての暗躍が後の日本を決定的にまずい方向に向かわせてしまう。
凡太: その人、お札の肖像になっていませんでしたっけ?
イシ: 500円札だね。私の世代は普通に使っていたけれど、よく知ってるね。
凡太: お札の肖像になった人物はクイズの問題によく出るんで覚えてました。
イシ: そういう知識だけは頭に入ってるんだな。まあいいや。
勅許を取ることに失敗した堀田正睦は、江戸に戻って将軍・家定に「この難局を乗り切るために、福井藩主・松平慶永を大老にしてください」と提案したんだけど、家定は「大老にするなら井伊直弼しかいない」と言って、急遽、井伊が大老に就任した。
江戸ではハリスと下田奉行・井上清直、外交担当の岩瀬忠震が13回に及ぶ交渉を続けて、日米通商条約の草案を練り上げていた。
ハリスは日記に、この条約の重要性を日本人に理解させるために経済学の基本から教えなければならず、それが大変だったと書いている。基本的な経済用語も日本語にはなかったため、その概念から説明する必要があった。
「商業は国の血液であり、命の泉です。イギリスを見なさい。貿易がなければあの小さな国の住民は餓死します。イギリスが世界を征服したのも、オランダが猫の額ほどの狭い国土ながら列強の一翼を担っているのも、すべては貿易のおかげです」
ハリスはそう説得し続けた。
おそらくその作業は、軍人のペリーでは無理だっただろうね。たたき上げの商人だったハリスだからできたんだと思う。
その間も、ハリスは様々な病気に冒されていて、常に死を覚悟しながら仕事をしているような状態だった。
そうした苦労の末、安政5(1858)年6月、ついに日米修好通商条約が締結された。
凡太: ペリーよりもハリスのほうが大きな役割を果たしたんですね。
イシ: そうだね。ハリスの外交能力は大したものだよ。
それと、この条約締結には、通訳としてハリスと一緒に来日した
ヘンリー・ヒュースケン(1832-1861)という青年も重要な役割を果たしている。
ヒュースケンはとても魅力的な人物だった。アムステルダム生まれのオランダ人なんだけれど、21歳のときに単身アメリカに渡ってアメリカ国籍を取得した。
渡米後は食うのもやっとという極貧生活だったんだけれど、日本渡航前のハリスがオランダ語の通訳を求めていることを知って応募し、採用された。
天真爛漫というか、誰とでも仲よくなれる天性の明るさと人なつこさを兼ね備えていて、交渉にあたった幕臣たちともうちとけ、友情のようなものさえ芽生えていたらしい。
オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語ができたので、日米通商条約締結後は、他国の領事らからも気に入られて、イギリスやプロシアとの修好通商条約締結にも協力している。
文才もあって、日記にはユーモアをまじえた洒脱な文章が残されているんだけど、日本と日本人が大好きになっただけでなく、日本の庶民を貧しい移民出身の自分に重ねて感情移入しているような描写もある。
例えば、下田を台風が襲って、漁船や家屋が破壊された後も、人々は悲嘆に暮れることなく、黙々と前を向いて復旧作業をしていた姿に感嘆している。
また、ハリスと共に江戸に向かう行列に対してひれ伏している人々を見て、自分より立派な人たちがなぜこんなに卑屈な姿を見せなければいけないのかと、残念な気持ちになったと書き残している。
凡太: あの密航してきた……マクドナルドさんに似てますね。苦労人で、日本が好きになった若者、という点で。
イシ: そうだね。幕府からも他の外国人たちからも好かれた人気者だったヒュースケンだけど、その後、公使館に帰る夜道で薩摩藩士らに斬られて亡くなっている。まだ28歳の若さだった。
幕府は見舞金として4000ドル、遺族である母親に弔慰金6000ドルを支払って事件を収拾させたんだが、幕府側にも諸外国の側にも大きなショックだった。
その後もこうしたテロ行為は続いていく。まったく何をやってくれてるんだと、本当に腹立たしいし、情けないよ。

ヒュースケン暗殺 (チャールズ・ワーグマン:画)
日米修好通商条約は「不平等」条約ではなかった
凡太: ハリスさんもヒュースケンさんもすごい人だったんですね。でも、彼らが結んだ条約は不平等条約で、その後、日本をずっと苦しめることにもなったんですよね?
イシ: 学校では今でもそんなふうに教えているのか。それは間違いだよ。
凡太: え? 違うんですか?
イシ: 全然違う。明治政府以降の「明治史観」に基づいて歪曲された説明だな。
不平等だという根拠は、
- 外国人居留地制度が設けられ、アメリカ側に領事裁判権を認めてしまった
- 日本に関税自主権がない
……というものだけれど、1)に関しては、当時の日本国内は薩摩や水戸藩の単純思考攘夷論者というか、そもそも思想とさえいえないような感情で動く直情型武士が見境なく外国人を襲撃して殺しているような状況で、外国人居留地区をもうけないほうが非人道的だし、非現実的だった。
裁判権にしても、当時の日本の処罰は諸外国に比べて残虐で、幕府に都合の悪い政策論を発表しただけでとらえられ、まともな裁判もなく、拷問を受けて獄死させられるような状況だったからね。常識も慣習も違う外国人を適切に裁いて処罰するなんてことは到底できなかっただろう。
2)に関しては、関税率は当初は日本側が主導して輸入税を20%(酒類は35%、日本に居住する外国人の生活必需品5%)と決めていて、この税率は当時としては日本にとって不利なものではなかった。アメリカを除く欧州列強国が相互に決めていた税率と同等だ。ちなみにアヘン戦争後の清国は5%、植民地化されていたインドは2.5%だから、そういう水準とは比べものにならないくらいちゃんとしている。
さらには「神奈川開港の5年後に日本側が望めば、輸入税ならびに輸出税は改訂しなければならない」という規定も盛り込まれていて、日本側が提起すればアメリカはその税率改定に同意しなければならない。アメリカ側が日本の関税率を改定しろと提起する権利は記されていないから、関税自主権がない不平等条約だというのは正しくない。
当時の日本の状況ではそれ以上は望めないというくらいまともな内容だった。
それなのに、単純思考の
攘夷派武士らが次々に外国人を殺害するなどのテロ行為を繰り返したため、幕府が関税引き下げ交渉を余儀なくされていく。日米条約の後に次々に締結された欧州列強との条約でも、不利な条件をごり押しされる理由を与えてしまった。イギリスとの条約では、イギリスの主力輸出品目である綿製品と羊毛製品の税率が5%にされてしまった。
凡太: 外国人排斥を叫んで暴れた人たちのおかげで、ますます外国との取り引きが不利になっていったということですか?
イシ: そういうことだね。外国人殺害テロをすればするほど、日本は野蛮な未開の国だということになって、諸外国に弱みを見せてしまうことになる。
そもそも、ただただ
尊皇攘夷を叫んでいた連中には欧米列強と交渉で渡り合えるような人材は皆無だった。無責任に暴れて鬱憤晴らししているだけのような連中のおかげで、日本はどんどんピンチに追い込まれていったんだ。
それに目をつけたのがイギリスだ。
イギリスでは軍部が1864(文久4)年に対日戦争計画を立案している。
日本の海上交通の通り道である瀬戸内海を封鎖し、天皇のいる京都を制圧。反撃できないように大坂城を艦砲砲撃して潰してから歩兵部隊を上陸させる。それが完了したら次は江戸で、幕府が築いた砲台を破壊した後は1万2000人の兵を上陸させて江戸城に迫り、焼き落とす……という大胆かつ具体的なものだった。(「日本における我々の立場に関する軍事覚書」英陸軍省ミシェル少将らの立案・報告書)
イギリスは他の国、特に対馬に進出してきていたロシアを牽制するためには、何がなんでも日本を思い通りに動かす必要があると決意していたんだ。
この
イギリスの武力制圧策を断念させたのが優秀な幕臣たちだったんだよ。特に外国奉行、軍艦奉行などを歴任した
小栗忠順の存在が大きい。
オランダを通じてイギリスやロシアの情勢を掴んでいた幕府は、オランダから買い入れた軍艦・開陽丸には、イギリス艦隊が搭載していたアームストロング砲(射程距離3km超)をしのぐクルップ砲(射程距離約4km)という最新鋭の大砲を搭載していた。
それを知ったイギリスは、武力による征服ではなく、経済的な支配で日本に傀儡政権を作るという方策に切り替えた。
自分たちが直接手を下すことなく、単細胞な武士のグループを利用して幕府を倒せば、その後はうまく操れる国にできると踏んだんだろう。
イギリスはすでに植民地化に成功した太平洋沿岸諸国や、アヘンでボロボロにした末に簡単に乗っ取れた清国で経験済みだからね。
日本は優秀で誇り高き武士たちが政権中枢にいて、侵略戦争を仕掛けても簡単には落ちない。それなら、反幕府勢力を使ったクーデターを起こしたほうがいい、とね。
日本崩壊序曲は水戸藩から始まった
日本にとって不運だったのは、この
重要な局面で、幕府内の足並みが揃わなかったことだ。対外政策に集中しなければいけないときに、将軍の後継ぎ問題なんかで無駄なエネルギーを使ってしまった。
凡太: それは学校の授業でも習いました。南紀派と一橋派の対立ですよね。
イシ: うん。教科書では単に将軍選びで、徳川慶福(後の14代・
家茂)を将軍にしたい南紀派と、一橋慶喜を将軍にしたい一橋派が対立したと書いてあるだろうけれど、実際にはそんな単純な対立ではなかったんだ。
まず、南紀派は、井伊直弼を筆頭に、会津藩主・松平
容保、高松藩主・松平
頼胤、老中・松平
忠固らの他、江戸城内の隠れた勢力ともいえる大奥も南紀派側についていた。南紀派は、幕府の力を弱めることなく、対外的には開国路線を継続的に模索していくという方向を描いていた。
一方の一橋派は、慶喜の父親である徳川斉昭を筆頭に、実兄の水戸藩主・徳川慶篤、越前藩主・松平慶永(春嶽)、尾張藩主・徳川慶勝、薩摩藩主・島津斉彬、宇和島藩主・伊達宗城、土佐藩主・山内豊信ら、名だたる諸侯が顔を揃えている。
ところがこの対立構図にはいくつもの「ねじれ」があるんだ。
まず、一橋派の筆頭・徳川斉昭はゴリゴリの攘夷派だけれど、薩摩の島津斉彬や宇和島の伊達宗城は開国を模索していた。
さらには、将軍に推されている当の慶喜自身は父の斉昭に「骨が折れるので、将軍になって失敗するより、最初から将軍にならないほうが大いによい」という手紙を書き送ったりしていて、全然乗り気でなかった。しかも、慶喜自身は父の斉昭の攘夷一辺倒には呆れていたようで、当時から、内心は開国やむなしという考えだったと思える。
つまり、徳川斉昭を除けば、南紀派と一橋派の政策はそんなに違っていたわけではないんだ。
見方を変えれば、徳川斉昭というゴリゴリの攘夷派がいなければ、あるいは斉昭が慶喜の父親でなければ、水戸藩と井伊直弼の対立や井伊の暗殺なども起きなくて済んだのかもしれない。
凡太: 安政の大獄と桜田門外の変ですね。
イシ: うん。「安政の大獄」というのは、「大獄」という言葉のニュアンスからして、井伊直弼が悪政を働いて、自分に逆らう政敵を次々に弾圧した……という印象を与えるものだけれど、それは一方的な教育プロパガンダだよ。
直弼の政策自体は基本的には間違っていなかった。
具体的には、
- 天皇を据えた日本式公武合体政治で、国力をつけながら諸外国と対峙していく。
- 植民地化される恐れのある欧米列強との武力衝突だけはなんとしてでも避ける。
というもの。
日米通商条約を結ぶに際しても、むしろ最後まで勅許にこだわっていたのは直弼だった。
将軍後継者問題にしても、何がなんでも徳川慶福にすべきだというのではなく、「徳川斉昭の息子だけは避けたい」という思いからのことだっただろう。
斉昭は大奥にも嫌われていて、斉昭が江戸城に来ること自体に大ブーイングが起きていたほどだった。
慶喜を将軍にしてしまったら、あの徳川斉昭が慶喜の裏で大御所政治のようなことを始めるだろう。そんなことになったら日本はとんでもないことになる、と。
実際には慶喜は父親とはまったく正反対の性格で、むしろ直弼ともうまくやっていけた可能性が高いと思うよ。
しかし、とにかく
朝廷側があまりにも無能、単純、無責任で、幕臣たちが必死に外交対応をしている先から、それを台なしにするようなことばかりしている。そこに斉昭が入り込んでさらにかき回す。
そうしたストレスが溜まっていたところに、朝廷から正式な手続きも経ないまま、水戸藩に「勅許なき条約調印を批判し、断固攘夷を断行せよ」という内容の密勅が出た。いわゆる「戊午の密勅」というやつだね。斉昭や、攘夷論一辺倒の国学者、そして岩倉具視ら中位・下位の公家たちが裏で工作して、とにかく異国嫌いの孝明天皇をたきつけたんだろう。
これで直弼がぶち切れてしまった。我々がこんなに辛抱強く努力しているのに、何も分かっていない無能で無責任な馬鹿どもがなんてことをしてくれてるんだ! と怒り心頭。攘夷論者や一橋派の人間を徹底的に処罰しまくる。
その対象には一橋派だというだけの理由で、有能な幕臣や他藩の人材も多く含まれていた。特に、
橋本左内を失ったのは大きかった。これから日本の知恵袋として活躍していくことができた逸材なのに、わずか25歳で斬首されてしまう。もはや井伊直弼の精神状態はまともではなかったのかもしれないね。
阿部正弘がいれば緩衝材の役割を果たしたかもしれないのに、そうなる前に37歳の若さで死んでしまったからねえ。
国が大ピンチを迎えているときに大切な人材がどんどん死んでしまったのが本当に残念だね。
ともかく、井伊直弼のぶち切れ行動がますます攘夷論者や倒幕派の公家や諸藩に火をつけてしまった。
その結果が桜田門外の変。
井伊直弼暗殺は、過激浪士らに「テロで解決すればいい」という最悪の刷り込みをしてしまった。以後、国内ではどんどんテロが横行していき、取り返しのつかない状況に陥ってしまう。
凡太: なんだか……徳川斉昭という人が災厄をまき散らした原点みたいですね。
イシ: この時期の水戸藩は困ったことばかりしている。いちばん影響力が大きかった斉昭は安政の大獄の年に死んでしまった。斉昭の腹心で、水戸藩内だけでなく国内の攘夷派の精神的支柱となっていた水戸学の藤田東湖も安政の大地震のときに死んでいて、後は野となれ山となれ状態。
水戸藩では、藤田東湖の四男・藤田小四郎が過激な尊王攘夷派の水戸天狗党を率いて挙兵し、北関東一帯の住民に多大な被害を与えた挙げ句に自滅。その後は水戸藩内で天狗党と対立していた保守派の諸生党が藩内に残っていた天狗党の家族ら400人あまりを、赤ん坊まで含めて皆殺しにするというとんでもない虐殺行為に走っている。安政の大獄どころじゃないね。
そういうのをしっかり見ていた諸外国は、
日本を支配するには内乱を利用するのがいちばんいいと考えたんじゃないかな。
尊皇だ攘夷だと叫んでテロや虐殺を繰り返した連中が、日本をどんどん窮地に陥れたんだよ。
そうした
付和雷同激情型の連中は、カリスマ性のあるリーダーに心酔する。
ここで私たちが学ぶべきことは、妙にカリスマ性のある人物には注意が必要だということかな。当人はよかれと思って行動しているのかもしれないけれど、そういう人物が、直接間接を問わず、人々のためを思って地道に努力する優秀な人たちを葬り去り、最終的には庶民を不幸に導くということが多々ある。
そして、勝者になった後は、カリスマ性だけが誇張されて歴史に書き込まれる。
大河ドラマなんて、本当に罪作りだよ。