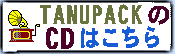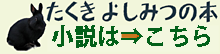人生という「時間線分」
人にとっての時間は、流れていく速さが一定でないだけでなく、「長さ」もまた相対的で、変化しうるものです。
すでに死んでしまった人の人生は、生年月日から死亡年月日までの時間の長さが確定しています。時間の長さを線で表せば、人生という時間を「線分」で表現できると思いますので、ここでは「
時間線分」という言葉を使ってみます。
死んでしまった人の人生の時間線分は確定していますが、今生きている私たちは、死亡年月日が確定していないため、人生の時間線分が片方に伸び続けています。
しかし、私たちが自分の人生を考えるとき、起点(生まれた瞬間)から終点(死んだ時点)までの時間線分「だけ」を限定的にとらえてもあまり意味はありません。
なぜなら、
自分が生まれる前、死んだ後も時間は流れていて、線分の前後の時間軸との関係性において私たちの人生もさまざまな意味を持ち、変化しうるからです。

↑人生の「時間線分」
父親と母親の人生がなければ生まれてきませんし、私たちの死によって、その後流れていく時間にも何らかの影響があるはずです。
ですから、
人生を考えるには、自分が生まれる前と死んだ後の時間も考えるべきです。
言い換えれば、
歴史を学ぶことの重要性。
自分の親や祖父母の時代に何が起きていたのか、この国はどんな空気に包まれていたのかを知らないまま大人になるというのは恐ろしいことだと思います。
生まれる前の時間を含めて人生の相対性を探る
私はどうも記憶力に欠陥があるようで、学生時代には社会科が大の苦手でした。苦手意識のある科目はどれだけ時間を割いても頭に入らず、試験ではいつも赤点のボーダーライン上をうろうろしていました。
大学入試では社会科の選択受験科目に日本史を選びましたが、それは単純に、世界史よりも暗記する項目が少なそうだと考えたからです。
それほど歴史、地理、法律、経済といったジャンルのことを勉強するのは苦痛だったのですが、歳を取るにつれ、なぜもっと歴史をしっかり勉強しなかったのかと後悔しています。
特に、近現代史をしっかり学ばなかったのは痛恨の極みです。今でも基本的なことを呆れるほど知りません。
もっとも、学校でまともに近現代史を教えてくれなかった、ということもあります。縄文土器と弥生土器の特徴とか荘園制度とか租庸調とかの知識は記憶に叩き込まれていても、近現代史に入る頃には授業の残り日数がなくなり、「後は自分で教科書読んでおけ~」で終わった、という経験は私だけではないでしょう。
近現代におけるヨーロッパ列強とアジアの関係。アジアの中で日本は何をどうしようとしていたのか。まだ生きた証言者がいるほんの数十年前のことを知らないのです。
ソウルオリンピックの開会式で、聖火を片手に競技場に小躍りしながら入ってきた老人の姿を覚えているでしょうか。記憶力の弱い私が今でも鮮明に覚えている出来事の一つです。
あの老人は孫基禎(ソン・ギジョン)さんといって、1936(昭和11)年のベルリンオリンピック男子マラソンの優勝者です。当時、朝鮮は日本に併合されていたため、日本代表選手として胸に日の丸をつけて出場しての金メダルでした。
Wikiにはこのときのことがこう記されています。
大会直後に朝鮮の新聞「東亜日報」に胸の日の丸が塗りつぶされた表彰式の写真が掲載され、当時の朝鮮総督府の警務局によって同紙記者の逮捕・発刊停止処分が下された。また社会部長だった玄鎮健も逮捕された。このため、10月になって帰国した孫には警察官が張り付き、朝鮮内で予定されていた歓迎会も大半が中止された。
孫自身は当時より民族意識が強く、世界最高記録樹立時の表彰式でも「なぜ君が代が自分にとっての国歌なのか」と涙ぐんだり、ベルリン滞在時には外国人へのサインに「KOREA」と記したりしていた。このうち後者は当時の特別高等警察によってチェックされて「特高月報」に記載されており、帰国後に「要注意人物」として監視を受けることにも繋がった。そのため、翌年明治大学専門部法科に進むが競走部への入部は認められなかった。
そうした背景を私は知っていましたから、彼が競技場に現れたシーンを見て涙がボロボロこぼれたものです。
ソン・ギジョンさんが喜びを全身で表現しながら競技場に入ってきたあの「時間」は、私の人生の時間線分の中に含まれる出来事ですが、あの感動は、
私が生まれる前の時間(歴史)がなければ成立しない感動です。
今の自分を起点にして近現代史を学び直す
自分が近現代史を知らなすぎるという致命的な知の欠落を少しでも補うべく、私は普段の生活の中で遭遇した出来事や情報の断片を糸口にして、生(ナマ)の日本史、世界史を勉強し直すように心がけています。
例えば、最近、日光中禅寺湖畔にある「イタリア大使館別荘記念公園」というところに行きました。
旧イタリア大使館別荘は、壁や天井に杉の皮を貼った情緒ある木造建築で、設計者はチェコ(当時はオーストリア=ハンガリー帝国)に生まれ、後にアメリカ市民権を取ったアントニン・レーモンド(1888-1976)という人です。
レーモンドは一般には「日本の木造建築をこよなく愛し、日本各地に優れた建築物を多数残した」といった評価をされています。
しかし、さらによく調べていくと、レーモンドは第二次大戦中アメリカに戻っていたとき、焼夷弾による東京大空襲の実験に協力するため、ユタ州の砂漠に東京下町の木造家屋の続く街並みを極めて緻密に再現した、という話が出てきました。
木造家屋が中心の日本の街並みを「効率的に破壊」するために焼夷弾が開発され、その開発実験に協力した日本通の建築家がいたことは知っていたのですが、その人物がイタリア大使館別荘の設計者だったということは見過ごすところでした。
今回、彼の作品の一つを見たことにより、より詳しく調べてみて、さらにいろいろなことが分かりました。
焼夷弾の開発はロックフェラー財閥傘下のスタンダード石油会社によるものであること、レーモンドが帝国ホテルの内装担当として東京に滞在しているときに関東大震災と大火災を経験していること、彼の家族は全員、第二次大戦中にナチスドイツの手で殺されたり戦死したりしていること、後に自伝の中で「戦争を最も早く終結させる方法は、日本を可能な限り早く、しかも効果的に敗北させることだと考えた」と述べていること ……などなど。
東京大空襲のとき、私の母は都内の聖路加病院で看護師をしていました。
全身焼けただれた負傷者を収容しきれず、廊下には呻き声を上げる人たちが寝転がされていました。
痛みを訴える人たち全員に与える薬はないため、病院はただの砂糖水を用意して、最初は砂糖水を「痛みが取れるお薬です」と言って与えたそうです。何人かの人たちはそれを薬だと信じて飲み「看護婦さんありがとう。おかげで楽になった」と言って眠りにつくのでそのままにして、それでも痛みを訴え続ける人にだけ本物の薬を与えたといいます。
このように、日々の生活の中で触れたことをきっかけに生の近現代史を知ると、
時代の時間軸における自分の幸福の相対性について考えざるをえません。
もし自分があの時代に生まれ、生きていたらどんな人生になっていたのか。
自分がレーモンドの立場だったらどう行動したか。
想像はどんどん広がり、人生とは、生きるとは、死ぬとは……といった問題をより深く考えるようになります。