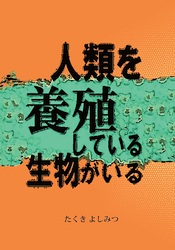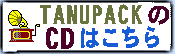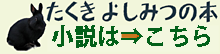宗教は「複層的世界観」を持てるか
「今あんたが言った『説明できない何かを感じる能力』とか、それを求める精神というのは、『
祈り』という行為につながっているんじゃないのか?」
俺はNにそう問いかけた。
<祈り……か……>
Nはその後の言葉を言いよどんだ。珍しく、考え込んでいるようだった。
しばらくして、Nは再び語り始めた。
<「祈り」という言葉は、人間の歴史の中では宗教というものと深く結びつけられてきた。今でもそれは変わらないだろう?
では、少し話が本題から逸れるかもしれないけれど、ここで、宗教というものについて、改めて考えてみようか。
いろいろな宗教があるが、概ね共通しているのは「神」という言葉に代表されるような「崇拝の対象」があるということだ。
でも、宗教は「神」が作ったものではない。人間が作ったものだ。
例えばキリスト教はイエスが作ったものではない。イエスはいろいろなことを語ったかもしれないが、それは「宗教」ではない。「キリスト教という宗教」はあくまでもイエスの死後に、イエスの回りにいた人間や、イエスの言動を伝聞で知った人間たちが作っていったものだ。
複数の人間が、時代を経て「編集」「改定」を重ねていくから、宗教はどんどん変質し、分化する。
歴史を学べば分かるように、主にヨーロッパにおいて、キリスト教は民衆を統治する道具としてどんどん作り替えられ、体系化されていった。布教する側は組織化され、多くの組織がそうであるように、中で階級や上下関係が生まれた。
キリスト教が成立してから長い間、キリスト教社会ではひとつの共通した世界観が形成された。
この世界は「神」が造った。あらゆる生き物も神の創造物である。神が最初から今の姿に造り上げていて、その中でも人間は神に選ばれた特別な存在である。
……そんな世界観だね。今ではこのタイプの世界観は「創造論的世界観」と説明されている。
しかし、科学が発展してくると、その考え方に異を唱える者が出てくる。
ダーウィンの「進化論」は、その例としてよく使われるね。
ダーウィンは、生物は時代の経過や環境の変化に合わせて「変化する」と考えた。
ここで間違えてはいけないのは「進化する」とは言っていないということだ。進化という言葉には、よりよきものになる、上等なものになる、というニュアンスが含まれるけれど、そういうことではない。
生物は環境に合わせて変化する。うまく変化できなかったものは環境の変化についていけずに種が絶えてしまうこともある、という説を主張しただけだ。
しかしこれは当時のキリスト教の組織にとっては認めがたい世界観だった。あらゆる生物は絶対的な存在である「神」が創造したものであって、最初から今の姿であることが決まっていた、という教えだったから。
魚は人間の食物となるために最初から魚の姿で造られている。ニワトリも同様に、人間がニワトリの肉や卵を食べられるように、あの姿で造られている。環境に合わせて変化するなどということはない、と。
絶対的な創造主がいて、人間はその絶対的な創造主の意志に従って生きていくのだ、というシンプルな世界観や教理を浸透させれば、民衆をまとめやすい、管理しやすい。
ところが、19世紀に産業革命が起きると、機械文明の発展でめまぐるしい社会変革が起きた。当然、人々の世界観も変わっていく。
ダーウィンが『種の起源』を出版したのは19世紀後半のことだ。彼の「生物は環境に合わせて変化する」という説は、いつの間にか「進化」という言葉に置き換えられ、人間も進化する、世界を変えていけるのだという考え方が、それまでよりもずっと受け入れられやすくなっていき、従来のキリスト教的な管理体系が通用しづらくなっていった。
人間が作った宗教にはいろいろな働きがある。
大きく3つあげるとすれば、まずは今言ったように、民衆を管理し、動かすための道具としての働きだ。
今のように情報伝達技術が発達していなかった昔は、大人数の人間をまとめ上げ、動かすための道具は同調圧力と宗教が中心だった。
人間は不完全な生き物だから、悩んでも仕方がない。絶対的な存在の教えに従うことが絶対的な法則だと思い込ませることで、大人数を動かすことができた。
2つ目は薬物のような役割だ。
これは麻酔薬的な役割と覚醒剤的な役割に分かれる。
死という避けられない運命を持って生まれた人間が、死を恐れないようにするためのモルヒネ。
信仰という絶対的価値のためには、不合理、不条理と思えるようなことに目をつぶってでも突き進め!……そういう爆発的な、ときに暴力的な力を発揮させるための覚醒剤。
どちらも戦争や虐殺に利用できることに注意しなければいけない。
3つ目は組織力としての効果・効率。
一人ではできないことが、教会や教団という組織の力を使えばできるようになる。
例えば戦争孤児たちを見てなんとかしたいと思っても、一人の人間ができることは限られている。しかし、教会や教団といった組織の一員として動けば、孤児院をいくつも作ったり、その活動を国に援助させたり、広く寄付金を集めたりといった大がかりなこともできる。
組織に所属する宗教者の中には、その宗教の教理のすべてを必ずしも受け入れていなくても、バランスのとれた組織人として振る舞うことで組織の内外から人望を集め、自分の信念や理想に近い活動を実現している者たちもいる。組織と頭は使いようなんだね>
「うん、そのへんまでは異論はないよ。宗教は使い方を間違えるとろくなことにならない、ってことだな」
<ろくなことかどうかは価値基準の起き方次第だろうけれど、とにかく「絶対的なもの」ではない。人間が発明し、作りあげたものであり、人間社会の中で使われる「手段」のひとつだ。多くの人間が抱いている「神」のイメージとは本来関係がない。「神」が存在するとしても、いわゆる「宗教」の中にはいない。
おっと、なんでこんな話になったかというと、きみが「祈り」という言葉を出してきたからだったね。
祈りというものが既存の宗教の中で使われる祈りのことなら、その祈りは神とつながってはいない。宗教が「手段」である以上、祈りは手段の中の手段だ。
祈りという「手段」そのものにいい悪いはない。どう使うかが問題になる。しかし、多くの宗教者や信者が、そのことを認識していない>
「ちょっと待ってくれ。今あんたは『神』という言葉を再び使い始めた。Gではなく『神』だ。
あんたらも神というような超越的な存在を信じて……いや、
感じているってことか?」
<おお、鋭いね。
その通りだよ。我々は神ではないし、世界のすべてを把握しているわけではない。ただ、世界は、物質世界という単相の世界だけではなく、それを包み込むような多重の世界、複層的世界だろうということを感じている。
「神」が存在するとすれば、その複層的な世界全体を見通している、あるいは
構成している何かなのではないかと感じている。
だから、我々にとっての「神」は、きみたち人間が作った宗教の中にはない。
でも、宗教というもののすべてを否定もできない。なぜなら、宗教は手段であっても、
宗教的な要素の中には、複層的な世界観に通じるものもあると思うからだ。
例えばブッダが瞑想していた世界は、それに近いものだったのかもしれない。
ニーチェが「神は死んだ」と言ったときに見つめようとしていたものこそ「神」だったのかもしれない。であれば、「神は死んだ」という言葉こそ彼にとっての「祈り」だったのかもしれない。
そういう意味での「祈り」ならば、「神」に通じるのかもしれない。
そう考えたとき、一言で「祈りは手段にすぎない」とは言えなかったんだよ。
宗教を「手段」にすぎないと断言することは、まさしくGの思考だ。
我々はGとは違う世界観を持っている。そして、人間にも同じような親近感を抱いている。
だから、人間が作りだした宗教というものの中にも、そうした要素が入っていてほしいと願っている。それもまた、我々にとっての「祈り」なのかもしれないね>
本になりました! 書籍版が最新の内容です 応援してください!