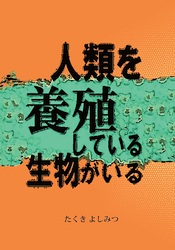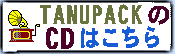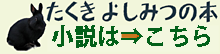アダムは「失敗作」だった
「アダムやセツが個人の名前ではなくて『神』が実験的につくりだした生物種の名前で、その何代目かがジェットへりみたいな乗り物を操るくらいの知能や技術を持つに到った……そういう話だよな。それなら、人間なんて必要ないんじゃないのか、と」
俺はNの言葉をほとんどそのまま繰り返した。自分がしっかり理解するために必要だったからだ。
<そういうことだね。
「神」がこの星以外のどこかからやってきて、この星で生存したいというだけなら、人間なんて必要ない。
神が草食なら、草木が生えているだけでいい。肉食なら、牛や豚のような家畜がいればいい。しかも、アダムのような「使える」生物もつくることができた。それで十分なはずだよね。それ以上、中途半端に知恵をつけた人間のような生物をつくったら、生態系のコントロールが面倒なことになりかねない。
それなのに、彼らはアダムよりも能力的にずっと劣っている人間という生物種もつくった。なぜだと思う?>
「多くの労働力が必要だったんじゃないか? アダムやセツだけでは足りなくて、その下で働く単純な労働力が」
<おお、素晴らしいね。そういうことだよ。足りなかったというより、アダムは失敗作だったんだ。
アダムには生殖能力が備わらず、自分たちだけで繁殖できなかった>
「聖書に書いてあるように『産めよ増やせよ』と神が言っても、それに応えられなかったと?」
<そうなんだ。これはもう、致命的だろう?
聖書は実に混沌とした内容で、読み解くのがやっかいだけれど、よく読めば、二つのことが共通して語られていることに気づくはずだ。
ひとつは『神は自分の姿に似せて人間を作った』ということ。
これには、すでにきみも気づいていると思うけど、今で言うクローン技術や遺伝子工学といったものが使われている。
同じ遺伝子情報を持つ肉体を再生産できるなら、生殖行為によって子孫を増やす必要がなくなる。優秀な遺伝子だけを選んで残していくこともできる。
「神」自身が自分たちの寿命を延ばすためにもそうした生命工学を駆使してきた。
その結果、彼らはクローンで肉体を再生産しすぎて、性差というものをほとんど失ってしまった。
性を決定するXとYの性染色体のうち、Y染色体は、X染色体に比べると欠損が多く、情報量が減ってきているというのは知っているかな?>
「ああ、なんか聞いたことはある」
<女性はXXで、同じ染色体が二つなので、一つに欠損ができてももう一方が補える。でも、Y染色体は常に一つしかないので、欠損が起きたときに補ったり修正したりできないまま次の世代に引き継がれやすい。その結果、長い時間を経ていくと、情報量がどんどん減ってしまうんだよね。
ましてやクローンで肉体の再生産を繰り返していくと、コピーのエラーが積み重なって、全体的には劣化する。
コンピュータのデータファイルはデジタル信号だから完全なコピーが作れるけれど、何回もコピーしていくうちにエラーが増えていって、気がつくとデータがあちこち壊れてしまっているというのと同じ理屈さ。
自然な生殖行為による生物種の維持も、Y染色体のコピーエラーが重なっていくことによって男の生殖能力は全体的に少しずつ落ちていく。最後は子孫を残せなくなって、種が絶滅する。
個々の生物に寿命があるように、生物種全体にも寿命がある。その宿命からは、なかなか逃れられないのさ。
「神もそういう運命をたどったというわけか?」
<そういうことだ。「神」の肉体はひ弱なんだよ。絶対的な生存数も少ない。
彼らは自分たちの種としての寿命を延ばすために新天地を求めてこの星にやってきた。でも、この地球上に自分たちがかつて築いたような物質文明社会をゼロから再構築するには、屈強な肉体とまともな繁殖力を持つ生物が必要だった。
アダムはもともとこの地球にいた生物を改造して自分たちの肉体に近づけた試作品だったんだけど、うまくはいかなかった。生殖能力が弱くて、普通には増えてくれない。だからアダムのクローンを作った。それがセツだね。
創世記第五章に「アダムは130歳になったとき、自分の形に似せた男の子を産み、セツと名づけた。アダムはセツを生んだ後、800年生きて、他に男子と女子を産んだ」という記述があるのを思い出してくれ。そんなに長く生きて、産んだ子供はたったの3人かい、って思わなかった?>
「そうだよなあ。930年で3人じゃあ、子孫がなかなか増えていかない」
<実は、その「産んだ」というのは古代人の理解に合わせた表現でね。アダムが「自分の形に似せた男の子を産んだ」というのは、神がアダムのクローンを作ったということなんだ。
アダムには神の遺伝子が入っているので、神ほどではないけれど長命なんだが、生殖能力はなかった。豹とライオンを交配させてできたレオポンが繁殖できないというのと同じだね。
そこで、アダムのクローンを作った後、神はアダムの肉体を使ったクローンをさらに改造して、男女の性差をつけようとした。
そういう実験を初期の頃は繰り返していたんだね。それを伝えているのが創世記第五章なんだよ。
何百歳まで生きたとか、何年目で子供を産んだというのは、つくり出したその生物種の寿命や、子孫を残せるか、残せそうもないと分かって、やむなくクローンを作ったが、その時期はいつかといったことが重要だから書いている。
ついでにいえば、創世記第六章は有名なノアの方舟の話が中心なんだけれど、洪水の話になる前に「ネフィリム」という興味深い生物の話がチラッと出てくる。
さて、地上に人が増え始め、娘たちが生まれた。
神の子らは、人の娘たちが美しいのを見て、おのおの選んだ者を妻にした。
そこで神は言った。
「わたしの霊は人の中に永久にとどまるべきではない。人は肉にすぎないのだから」
こうして、人の一生は120年となった。
当時もその後も、地上にはネフィリムがいた。これは、神の子らが人の娘たちと交わって産ませたものであり、大昔の名高い英雄たちであった。
……面白いよね。アダムから始まった改造生物種がその後どうなっていったかがうかがい知れる記述だ。
「神の子
ら」と複数形で書いているから、初期型の改造生物種に何度も手が加えられ、実験が繰り返されるうちにある程度の数になっていたことが分かる。それらが人間の女性と性交し、子供を産ませたということだね。そうして生まれたのがネフィリム。「天から落ちてきた者たち」という意味だ。
実は、アダムからつくった最初の子であるセツはクローンなんだが、その後、800年生きて生まれた男子と女子というのは人間の女性に産ませたネフィリムだ。ネフィリムだから性別がはっきりしているので、男子と女子なんだ。
でも、ネフィリム同士では繁殖できなかった。ネフィリムは人間に比べれば体力や知力に優れていたから、英雄視される者もいたけれど、その能力にものを言わせて面倒を起こす者も出てくる。
神としては、自分たちの道具にしかすぎない生物種が中途半端に力を持って面倒を起こすことは許せなかった。「人は肉にすぎない」とか、寿命を大幅に短くしたといった記述は、神の苛立ちを表しているね。
こんな風に、神の実験は紆余曲折を経て、どんどん混沌としてくる。そこでついに神は短気を起こして、一度ガラガラポンをするわけだ。え~い、やめやめ。やり直し! とね。それが洪水とノアの方舟の話に込められている>
「なんかもう、トンデモな話だなあ。にわかには信じられない」
<うん、今は信じられなくていいよ。それでも、完全否定ではなく、半信半疑くらいなら嬉しいけれどね>
「じゃあ、そういうことにする。半信半疑。面白い話ではあるし。続けてくれ」
<ここまでの話をまとめてみようか。
神は自分の姿、つまり自分の肉体に近い生命体をつくりたかった。まったくゼロからつくり出すことはできないので、地球上にすでに存在していた生物種を利用してつくった。アダムやセツという名前は、その実験結果に生まれた生物第1号、第2号といった意味しかない。
でも、そうしてつくった最初の改造生物は、自分たちだけでは子孫を増やせないという点で「失敗作」だった。
ここまではいいかな?>
「ああ」
<そこで神としては、もっとこの地球環境に合った自然な生命力、繁殖力、適応力を持った生物種をつくって、自分たちが望む文明の基盤作りに利用する必要があった。
これこそが、彼らがこの星で
人間をつくらなければならなかった理由なんだよ>
「悲しい話だな。俺たち人間は、神にとっての労働力なのか?」
<単なる労働力以上のものだね。
彼らが地球にやってきたとき、所持していた道具や資材は極めて限られていた。だから、この星に彼らが望む社会基盤を作るには、地球の資源を使って「物」を製造する必要があった。
しかし、彼らはそれを実際に行うだけの屈強な肉体を持っていない。数も足りない。
その役割を担わせるつもりだったアダムは自分たちだけでは繁殖できず、失敗作だった。
そこで、人間という本来の地球の生物種に限りなく近い生物を作り、時間をかけて数を増やし、知恵をつけさせ、文明を築かせるという計画を立て、実行し始めた。
繁殖力を失わせないことと引き替えに、知能は劣る。でも、時間をかければ、自分たちが望むだけの技術を持ち、文明社会を築けるはずだ、と。
人類史というのは、こうして始まった。そして現在は、その最終段階にさしかかっている>
本になりました!